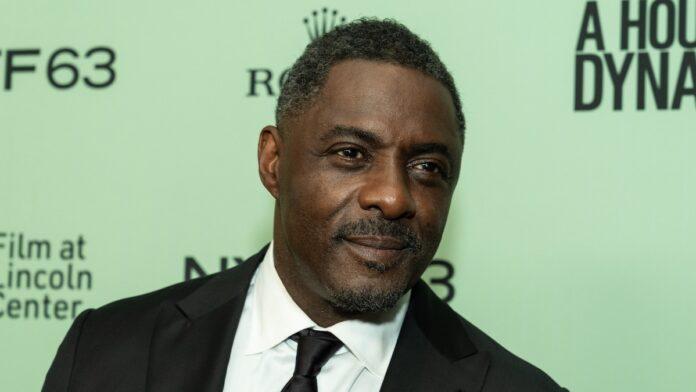ネットフリックスの新作映画『ハウス・オブ・ダイナマイト』は、発信元不明の大陸間弾道ミサイル(ICBM)が米国の都市を標的に発射され、迎撃に失敗する恐怖を描き、公開後に政府や議員を巻き込む論争を呼んでいる。
民主党のエド・マーキー上院議員はMSNBCへの寄稿で、映画が「当局者や政府が認めたがらない残酷な真実」を露わにしたと指摘した。マーキー氏によれば、米国のICBM迎撃システムは理想的な試験環境でさえ成功率が約55%にとどまる(映画では地上配備型迎撃ミサイルの命中率が61%と描かれる)。実戦では欺瞞(デコイ)や飽和攻撃、人為的ミスが加わるため、「完璧な防御」は幻想だとし、トランプ政権が掲げる巨額予算の「ゴールデンドーム構想」も「見せかけ」にすぎないと批判。軍備削減や戦略兵器管理を優先すべきだと訴えている。
これに対し国防総省側は映画の描写に異議を唱えている。ブルームバーグが入手したメモによれば、ミサイル防衛局(MDA)は「映画は観客を楽しませるためのドラマチックな演出」として迎撃に失敗する場面を描いているが、現実の試験結果は「全く異なる」と説明し、「10年以上にわたり、試験で100%の正確性を達成している」と実績を挙げて反論したという。
映画の制作側、監督のキャスリン・ビグロー氏はガーディアンの取材に対し、防衛体制に構造的な欠陥があると述べ、現場の人々が有能でも「無謬(むびゅう)ではない」と反論した。監督は国防総省の協力を得なかったものの、脚本家ノア・オッペンハイムとともに、政策専門家やジャーナリスト、元情報長官ら多様な情報源を参考に現実性の高いシナリオ化を目指したという。技術顧問には元陸軍将校で戦略軍司令部参謀長経験者のダン・カーブラー氏が名を連ねる。
迎撃ミサイルの命中率以外でも争点はある。劇中では発信元不明のICBMが衛星監視をかいくぐって発射されるが、オッペンハイム氏はタイム誌の取材で「衛星システムへの干渉」が現実的な手段になり得ると指摘した。一方、カーブラー氏は発信元不明の発射は過去に例がなく、宇宙配備赤外線衛星(SBIRS)の信頼性やシステムの冗長性により発見可能性は高いと述べている。
また、ICBMが大気圏再突入の終末段階に入ると地上迎撃の有効性は低下するのが事実だが、カーブラー氏は、イージス艦搭載ミサイルで終末段階の極超音速目標が撃破された試験例や、無人機を使った対処案、チャフ(細片)による攪乱といった対策の検討も続いていると指摘している。